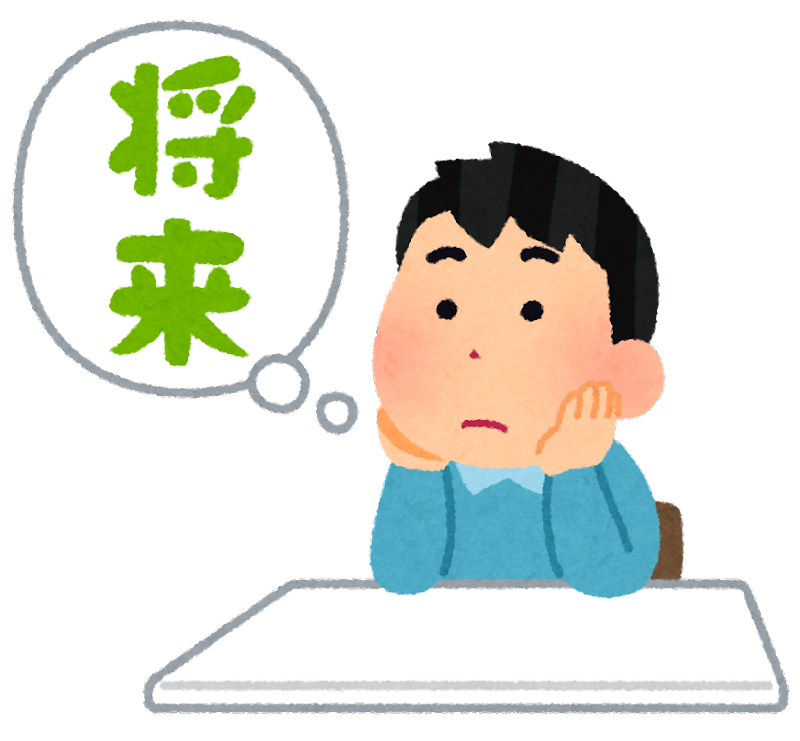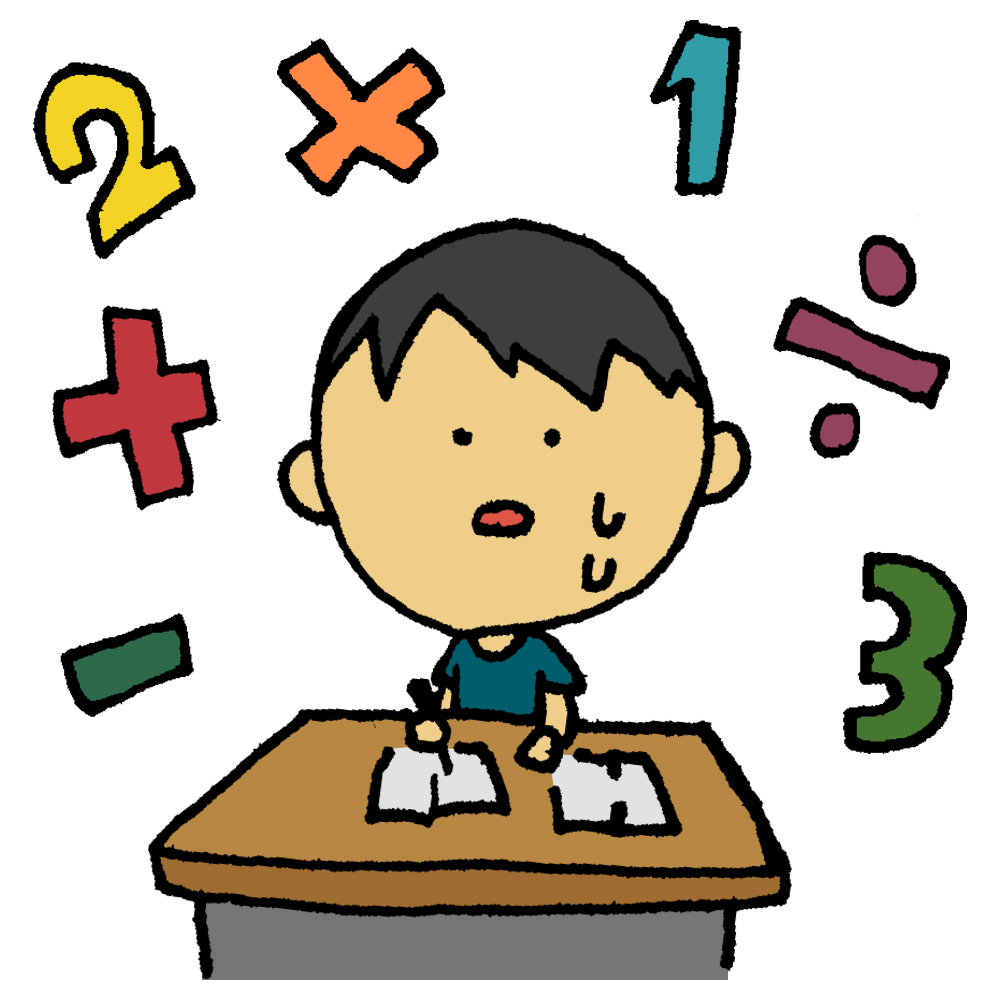目の前の子が定型発達児に追いつけるのか?
いつこの子の芽が出るのか?
本当に成果がでる日がくるのか?
ADHD児を育てる保護者や支援者にとって、このような不安を抱くのは当然でしょう。
多くの研究によりADHD児の脳の成長は定型発達児に比べて遅いことが判明しています。また、中学生や高校生になってADHD児の脳の成長がやっと追い付くことが多いのも明らかになっています。
将来きちんと芽が出るように種まきをしながら子どもの成長を待つというスタンスがよいようです。
◆ADHD児は発達がおそいのは本当なのか?
ADHD児では前頭前皮質や偏桃体、海馬の容積が定型発達児と比べて減少していることが研究により明らかになっています。これらの部位減少が15歳以下の小児においての顕著であるというデータも明らかになっています。
10歳から17歳のADHD児と定型発達児の皮質厚を比べた断続的研究では、ADHD児群は定型発達児群に比べて皮質厚さのピークが2年から5年の遅れがあることも明らかになっています。
・前頭前皮質…計画性や予測行動をつかさどる部位
・偏桃体…刺激反応をつかさどる部位
・海馬…記憶をつかさどる部位
ADHD児は社会性や学習をつかさどる部位の成長がゆっくりであることが、研究でわかっていることなのです。
◆どのように支援するのか
上述の通り、ADHD児の脳の発育は定型発達児と比べてゆっくりしていことはわかりました。しかし、中学生や高校生になってしっかり芽が出るように小学生のうちから正しい種まきをしておきたいものです。
まず、保護者や支援者はお子様の成長がゆっくりであることを理解しましょう。
思うようにお子様が行動しないときでも、お子様を怒ったり無理強いをすることは避けてください。
お子様もどうすることができないもどかしさを感じています。自分の不自由さを抱えながらも一所懸命に生活していることを認めてあげましょう。「大きくなったらきっとできるようになるよ」とやさしい言葉をかけてください。
そして、脳が健全に育つように根気強い支援を継続しましょう。
お子様によってADHDの特性はちがいます。お子様との遊びや勉強を通して、お子様の行動や思考の特性をよく観察してみましょう。
「あなたはこう感じているんだね。こんなふうに見えているんだね。」とお子様と共感するように接してみると、お子様の特性が手に取るように理解できるようになります。
お子様の特性がわかってきたら、脳の発育に良い支援のしかたを検討していくのです。
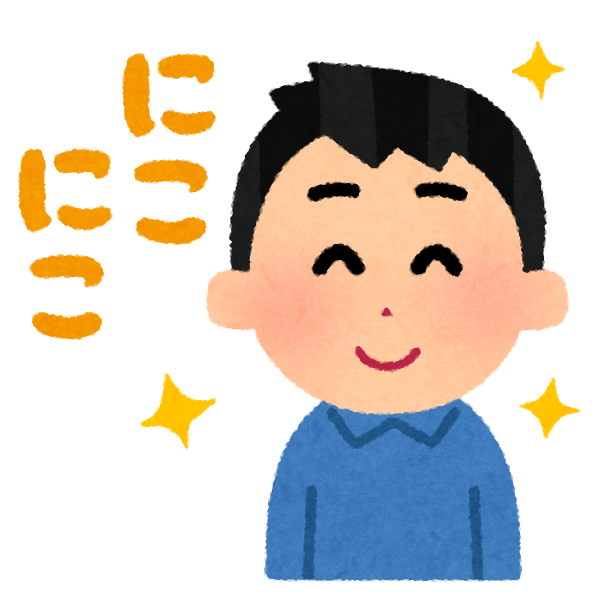
◆まとめ
お子様の特性をよく理解し、根気強く支援を続けていくことで、いつの日にかお子様の力が大きく花開くことでしょう。
保護者や支援者の不安な気持ちを明るい期待に切り替えて共に暖かい支援を行っていきましょう。
「どうしても他の子と比べてしまって保護者が不安な気持ちを拭えない。」
「自分のフィルターのせいでうちの子の特性を客観的に見れる自信がない。」
「うちの子の特性がわかったけど、何をしていいのかわからない。」
保護者がこのような気持ちを抱くことも正直なところでしょう。そのような時は、ぜひプロの支援者に頼ってみてはいかがでしょうか。
家庭教師和顔はお子様と一緒に遊び学び、お子様の特性をつかみ、期待の声をかけ、具体的な支援につなげていくお手伝いができます。
お子様の明るい未来を信じて一緒に寄り添っていきましょう。
◆参考文献
・庭野賀津子『注意欠如・多動症の支援に脳科学の知見を活かす』
・Wikipedia
・脳科学辞典